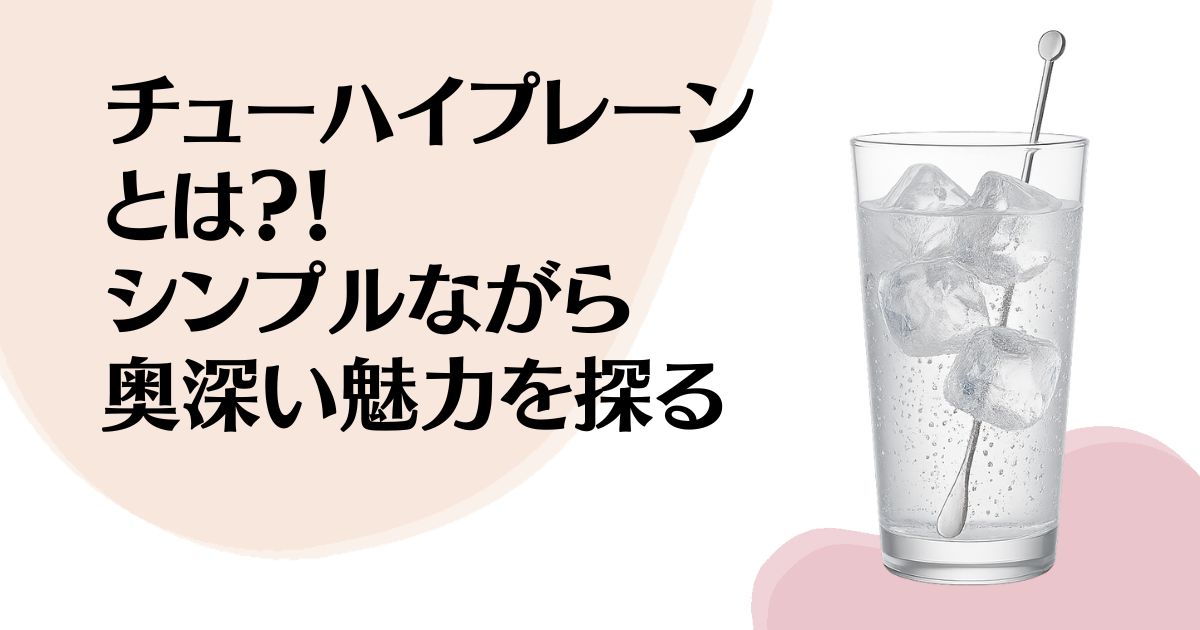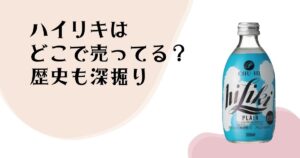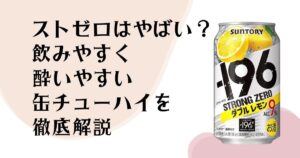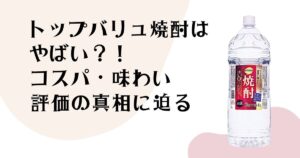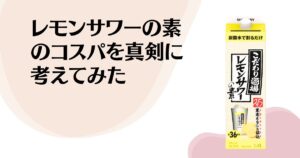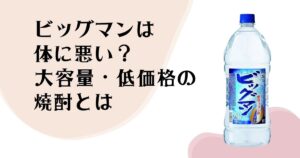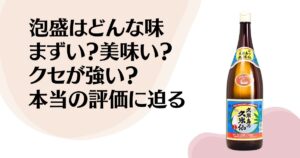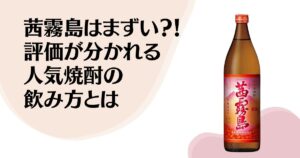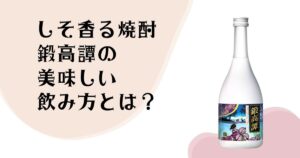【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】
チューハイ プレーンが何なのか気になっていませんか?
プレーンチューハイとは、焼酎を炭酸水で割っただけの非常にシンプルなお酒で、近年では缶タイプの商品も登場し、幅広い層に人気を集めています。
この記事では、プレーンチューハイに使われる焼酎の種類から、気になるカロリーや太るリスク、度数の目安、正しい作り方に至るまで詳しく解説します。
また、甘いのでは?という味わいについての素朴な疑問にも触れ、初めての方でもわかりやすいよう丁寧にまとめました。
さらに、関西に根付く独自のチューハイ文化や、手軽に楽しめる缶チューハイのおすすめ商品もあわせてご紹介します。
チューハイ プレーンの魅力を、シンプルだからこその奥深さとともに、じっくりお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
☑️プレーンチューハイとは何かをサクッと整理すると、こんなイメージです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プレーンチューハイとは? | 焼酎を炭酸水だけで割った、味付けなしのシンプルなお酒 |
| ベースのお酒 | 主にクセの少ない甲類焼酎 |
| 味わい | ほぼ無味でスッキリ。甘くない・香り控えめ |
| アルコール度数の目安 | 約6〜8%前後(割り方で調整可能) |
| カロリー・糖質 | 焼酎+炭酸水のみなので、比較的低カロリー&低糖質 |
| 特徴 | 料理の味を邪魔せず、どんな食事にも合わせやすい |
| こんな人におすすめ | 甘くないお酒が好きな人/食中酒としてお酒を楽しみたい人 |
- プレーンチューハイとは何か、その定義と特徴
- プレーンチューハイのカロリーや太るリスク
- 焼酎の種類や作り方、度数の調整方法
- 缶タイプの商品や関西のチューハイ文化との関係
チューハイプレーンの魅力と人気の理由

世界のお酒に溺れたい! イメージ
- プレーンチューハイとは何か?定義を解説
- プレーンチューハイに使われる焼酎の特徴と種類
- 甘い?実際の味わい
- 太るのか心配?注意点とは
- 気になるカロリーを比較してみた
プレーンチューハイとは何か?定義を解説
プレーンチューハイとは、焼酎を炭酸水で割っただけの、シンプルで無味に近いアルコール飲料を指します。レモンやグレープフルーツといったフレーバーが入らない、いわゆる“無味のチューハイ”です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
このように言うと「ただの焼酎の炭酸割りでは?」と思われるかもしれませんが、実際その通りです。
ただし、居酒屋などではこれを「プレーンチューハイ」「ノンフレーバーサワー」「素チューハイ」などと呼び、味付きのチューハイとは区別して提供しています。
プレーンチューハイの最大の特長は、何も加えない分だけ焼酎そのものの風味と炭酸の爽快感がダイレクトに感じられる点。
味の主張がないため、どんな料理にも合わせやすく、食事中のお酒として好まれています。
また、糖分や香料を加えないため、比較的カロリーや糖質が低く、健康志向の人にも支持されています。
とはいえ、アルコール度数はしっかりあるため、飲みすぎには注意が必要です。
このように、プレーンチューハイはシンプルだからこそ奥深く、食事との相性や自分好みの焼酎・炭酸で工夫できる自由度の高い飲み物です。
プレーンチューハイに使われる焼酎の特徴と種類
チューハイ プレーンに使われる焼酎の多くは、「甲類焼酎」と呼ばれる無色・無臭でクセの少ないタイプ。これは、連続式蒸留という製法で造られるため、アルコールの純度が高く、雑味が抑えられているのが特徴です。
このため、チューハイ プレーンでは、焼酎独特の風味が控えめになり、非常にクリアな飲み口になります。
飲み飽きしない味わいから、長時間ゆっくり飲みたいときや、食事に合わせて楽しみたいときにも適しています。
代表的な甲類焼酎には「キンミヤ焼酎」「JINRO」「宝焼酎」などがあり、いずれも手に入りやすく、価格も手ごろなため、家庭でもチューハイ作りに使われることが多いです。
一方で、プレーンチューハイに本格焼酎(乙類焼酎)を使うことも可能ですが、こちらは個性の強い風味が出やすく、人によっては好みが分かれます。
香りやコクを楽しみたい上級者向けともいえるでしょう。
このように、チューハイ プレーンで使う焼酎の種類によって味わいが大きく変化します。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
クセのないすっきりとした飲み口を求めるなら甲類焼酎を、個性ある味わいを楽しみたいなら乙類焼酎を選ぶと良いでしょう。

甘い?実際の味わい
プレーンチューハイは、基本的に「甘くありません」。むしろ、無味に近いさっぱりした味わいが特徴です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
プレーンチューハイとは、焼酎を炭酸水で割っただけのドリンク。そこに果汁やシロップなどの甘味料は入っていないため、味の主張が非常に控えめです。
多くの人が「炭酸水に近い感覚」と表現するのはこのためです。
例えば、甘い缶チューハイやジュース割りのカクテルを想像している方にとっては、最初は物足りなく感じるかもしれません。
しかし、料理の味を邪魔せず、飲み飽きないという利点があるため、飲み慣れると「これが一番落ち着く」と感じる人も多いです。
一方で、商品によっては「プレーン」と書かれていても、ほんのり柑橘系の香りや甘みが加えられている場合があります。
これは「味わい系プレーンチューハイ」とも呼ばれ、タコハイなどに代表されるタイプ。無味ではありますが、飲み口をまろやかにするための工夫として、香料やごくわずかな果汁が使われることもあります。
このように、甘さを期待してプレーンチューハイを選ぶとギャップを感じるかもしれませんが、甘くないからこそ長時間飲んでも重くならないのが魅力です。
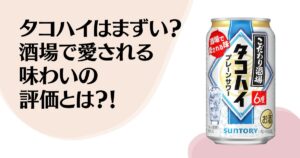
太るのか心配?注意点とは
チューハイ プレーンは、他のお酒と比較すると太りにくい部類に入ります。ただし、飲み方によっては注意が必要です。
まず、焼酎は蒸留酒のため糖質がほとんど含まれておらず、炭酸水にもカロリーはありません。
つまり、プレーンチューハイ自体には太る原因となる糖分や脂質がほとんどないのです。
そのため、糖質制限中の方やダイエット中の人にも選ばれやすいお酒といえるでしょう。
しかし、実際には「飲む環境」や「飲み方」によってカロリーの摂取量が増えてしまうことがあります。
たとえば、プレーンチューハイは飲みやすいため、ついつい飲みすぎてしまい、アルコールの摂取量が多くなると、肝臓はアルコールの分解を優先し、脂肪の代謝が後回しになるため、脂肪が蓄積しやすくなるのです。
さらに注意したいのは「おつまみ」。プレーンチューハイは揚げ物や味の濃い料理とも相性が良いため、高カロリーな食事とセットになりがちです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
お酒そのものは低カロリーでも、結果的に摂取カロリーが増えて太る原因になることがあります。
そのため、体重が気になる人は、おつまみに枝豆や冷奴などの低カロリーな食品を選ぶとよいでしょう。加えて、夜遅くの飲酒や寝る前の飲酒は代謝を下げるため、なるべく早い時間帯に楽しむことが大切です。
このように、プレーンチューハイは本来太りにくい飲み物ですが、習慣や合わせる食べ物によっては体重増加につながる可能性があるため、飲み方には注意が必要です。
気になるカロリーを比較してみた
プレーンチューハイのカロリーは、他のアルコール飲料と比べて比較的低めです。これは、使用される材料が焼酎と炭酸水のみであることが大きな要因です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
例えば、一般的なプレーンチューハイ(焼酎60ml+炭酸水120ml)の場合、おおよそのカロリーは約90〜110kcal程度です。
これは焼酎のアルコール度数や使用量によって前後しますが、基本的に糖質や脂質を含まないため、低カロリーに分類されます。
一方、甘味料や果汁を含む市販の缶チューハイの場合、350mlでおよそ150〜250kcalほどになることも珍しくありません。
中には300kcal近いストロング系の商品もあります。これに比べると、プレーンチューハイのほうが圧倒的にカロリーを抑えやすいといえます。
さらにビール(350ml)は約140kcal、日本酒(1合:約180ml)は約180kcalほどなので、同じ量を飲んだ場合でもプレーンチューハイは低カロリーであることがわかります。
ただし、焼酎の量を多くすれば当然カロリーも上がります。また、飲み過ぎれば摂取エネルギーも増えてしまうため、「低カロリーだから安心」と思い込まず、適量を心がけることが大切です。
このように、プレーンチューハイはダイエット中でも比較的取り入れやすいお酒ですが、アルコールの量と飲む頻度には注意したいところです。
チューハイプレーンを楽しむための基礎知識

世界のお酒に溺れたい! イメージ
- 度数はどのくらい?
- プレーンチューハイの作り方と割り方のコツ
- 缶で買えるおすすめのプレーンチューハイ
- 関西で人気のチューハイ文化とは
- プレーンとサワーの違いを整理
- プレーンチューハイと食事の相性を解説
度数はどのくらい?
プレーンチューハイのアルコール度数は、使う焼酎の種類や割り方によって変わりますが、一般的には6〜8%前後。
居酒屋などで提供されるプレーンチューハイは、飲みやすさや食事との相性を重視して、アルコール度数を7%前後に調整している場合が多く見られます。缶タイプの製品でも、タコハイのように6%に設計されたものが一般的です。
自宅で作る場合には、焼酎と炭酸水の割合によって自由に調整できます。例えば、25度の甲類焼酎を「1:2(焼酎1に対して炭酸水2)」で割った場合、完成したプレーンチューハイの度数は約8.3%になります。もっと軽めにしたい場合は「1:3」など、炭酸の比率を高めれば約6.2%となりアルコール感を抑えられます。
このように、プレーンチューハイは好みに応じて度数の調整がしやすいのが魅力です。ただし、焼酎の原液はアルコール度数が高いため、割り方によってはストロング系に近い仕上がりになることもあります。飲みすぎを防ぐためにも、1杯のアルコール度数を把握しながら楽しむと安心です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
プレーンチューハイの作り方と割り方のコツ
プレーンチューハイは非常にシンプルなお酒ですが、美味しく仕上げるためにはいくつかのポイントがあります。作り方自体は簡単で、基本の材料は「焼酎」と「炭酸水」の2つだけです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
まず、用意するのはクセの少ない甲類焼酎。
アルコール度数20〜25度のものが使いやすく、代表的な銘柄としては前述の通りキンミヤやJINRO、宝焼酎などがあります。
次に重要なのが割り方です。一般的なおすすめの比率は「焼酎1:炭酸水2〜3」。
濃い目が好きな方は1:2、軽めが好きなら1:3やそれ以上に薄めても構いません。
氷をたっぷり入れたグラスに焼酎を注ぎ、そのあと炭酸水を静かに注ぐのが基本です。最後にマドラーで軽く一回混ぜることで、炭酸の泡立ちを保ちつつ全体がなじみます。
ポイントは炭酸をできるだけ逃がさないこと。勢いよく注ぐと炭酸が抜けてしまい、爽快感が薄れます。
また、グラスや材料はあらかじめ冷やしておくと、よりキレのある味わいになります。
このように、ちょっとした工夫で家庭でも居酒屋のようなプレーンチューハイが楽しめます。シンプルだからこそ、焼酎の質や炭酸の強さ、注ぎ方が味に直結するのです。
缶で買えるおすすめのプレーンチューハイ
市販されている缶のプレーンチューハイは、手軽さと安定した味わいが魅力です。なかでも注目されているのが、サントリーの「こだわり酒場のタコハイ」です。
このタコハイは、プレーンチューハイでありながら、ほんのり柑橘の香りとやわらかな酒感が特徴。
無味に近いプレーンタイプよりも、少しだけ飲みやすさをプラスした「味わい系プレーンサワー」として開発されました。
使用しているのは焙煎麦焼酎で、香ばしさが感じられるのもポイントです。
缶タイプの魅力は、コンビニやスーパーで気軽に購入できる点と、氷や炭酸水を準備する必要がない点。
そのまま飲んでも良いですし、グラスに注いでアレンジを加えるのもおすすめ。
例えば梅干しやスライスレモンを入れると、自分好みのカスタマイズが可能です。
私も実際に飲んでみましたが甘くなくスッキリしていてとても美味しい!

実際のに飲んでみた
他にも、宝酒造の「焼酎ハイボール〈ドライ〉」もプレーン寄りの味わいで人気があります。こちらは甘さが一切なく、スッキリとした飲み心地を好む人にぴったりです。
このように、缶で買えるプレーンチューハイはバリエーションも増えており、気分や料理に合わせて選べるのが嬉しいところです。自宅で気軽に居酒屋気分を楽しみたい人には、常備しておくと便利なお酒といえるでしょう。
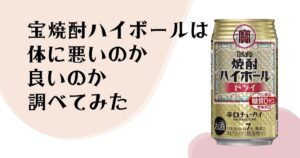
関西で人気のチューハイ文化とは
関西では、チューハイに対する呼び方や親しみ方が、関東とは少し異なります。特に「レモンサワー」ではなく「レモンチューハイ」や「チューハイレモン」と呼ぶ文化が根付いているのが特徴です。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
この呼び方の違いには歴史的背景があります。戦後の関西では、焼酎を炭酸で割った「チューハイ」が広まり、そこにレモンを加えたものが「レモンチューハイ」として親しまれました。
関東ではサワーという呼び方が浸透していったのに対し、関西ではあくまで「チューハイ」という名称が主流のまま残ったのです。
また、関西で外せない存在が「純ハイ」です。これは大阪・梅田の串カツ店「ヨネヤ」で生まれた、焼酎ベースの元祖チューハイで、タカラcanチューハイの開発元にもなったと言われています。
高齢の方の中には今でも「純ハイ」の名称を使う人も多く、ローカル文化として根強く残っています。
関西の居酒屋では、こうしたチューハイ文化が今も日常に溶け込んでおり、料理との組み合わせも重要視されています。
粉もんや煮物とチューハイを合わせるのは関西ならではの定番スタイルです。
このように、関西のチューハイ文化は地域性と歴史が色濃く反映されており、名前や飲み方にその土地の人々のこだわりが感じられます。関東との違いを知ると、より楽しく味わえるはずです。
プレーンとサワーの違いを整理
「プレーンチューハイ」と「サワー」は、どちらも炭酸で割ったお酒として似ていますが、細かな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理してみましょう。
ここまでお伝えしている通り、プレーンチューハイは、焼酎(主に甲類)を炭酸水で割っただけの非常にシンプルな飲み物です。
味付けは一切せず、無味に近いのが特徴。香料や甘味料も加えられていないため、すっきりとした飲み心地を求める人に好まれます。
一方の「サワー」は、焼酎やウォッカといった蒸留酒に、レモンやグレープフルーツなどの果汁、シロップ、さらには香料を加えて炭酸で割るスタイルが一般的。
味が付いている分、飲みやすく、バリエーションも豊富なのが魅力です。レモンサワーやカルピスサワーなどがその代表例です。
つまり、プレーンチューハイが「何も加えない素の状態」なのに対し、サワーは「味や香りを加えてアレンジされたスタイル」と言えます。見た目は似ていても、味の方向性や楽しみ方は大きく異なるのです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
このように、両者は原材料や目的に違いがあり、飲み比べるとその差がはっきりと分かります。どちらが良いというよりも、シーンや好みに合わせて使い分けるのが理想的です。
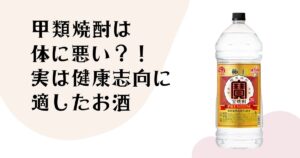
プレーンチューハイと食事の相性を解説
プレーンチューハイは、食事と合わせるお酒として非常に優秀です。その理由は、味にクセがなく、どんな料理の風味も邪魔しないからです。

世界のお酒に溺れたい! イメージ
特に脂っこい料理と好相性です。たとえば、餃子や唐揚げ、焼き鳥といった濃い味のおつまみでも、プレーンチューハイは口の中をすっきりリセットしてくれます。
炭酸の刺激が油を洗い流すような効果をもたらし、飲み続けても重たく感じにくいのがポイント。
また、繊細な和食とも相性が良いのが特徴です。お刺身や天ぷら、煮物など、味のバランスを大切にした料理にも合い、素材の風味を引き立ててくれます。
甘みや香りがないため、料理本来の味を変えることがありません。
もうひとつの利点は、食事のジャンルを問わない点。
和食はもちろん、洋食、中華、エスニックまで幅広く対応できるため、どんなメニューでも合わせやすい万能型のお酒といえるでしょう。
プレーンチューハイは、料理を引き立てつつ飲みやすさもある、まさに“食中酒”として最適な一杯です。外食だけでなく、家庭での晩酌にも活用しやすいため、冷蔵庫に常備しておくのもおすすめです。
チューハイプレーンの魅力と特徴をまとめて紹介
この記事のポイントをまとめます。
- チューハイ プレーンは焼酎と炭酸水のみで作る無味に近い酒
- 甘味料や香料を加えないためすっきりとした味わい
- 味の主張がない分、どんな料理とも合わせやすい
- 焼酎の種類により風味や飲み口が大きく変わる
- 甲類焼酎は無臭でクセがなくプレーンに適している
- 乙類焼酎を使うと香りやコクが強くなる傾向がある
- プレーンチューハイは基本的に甘くない
- 缶タイプのプレーンチューハイも市販されている
- タコハイや宝焼酎ハイボールは缶で人気の製品
- アルコール度数は一般的に6〜8%前後が多い
- 炭酸水の量で度数を自由に調整できるのが利点
- カロリーは他のアルコールよりも低めに抑えられる
- 太りにくいが飲み方やつまみによって注意が必要
- 関西では「レモンチューハイ」など独自の文化がある
- サワーとの違いは甘味や果汁などの有無にある